物理SIMとeSIM併用できる?4つのメリットと注意点
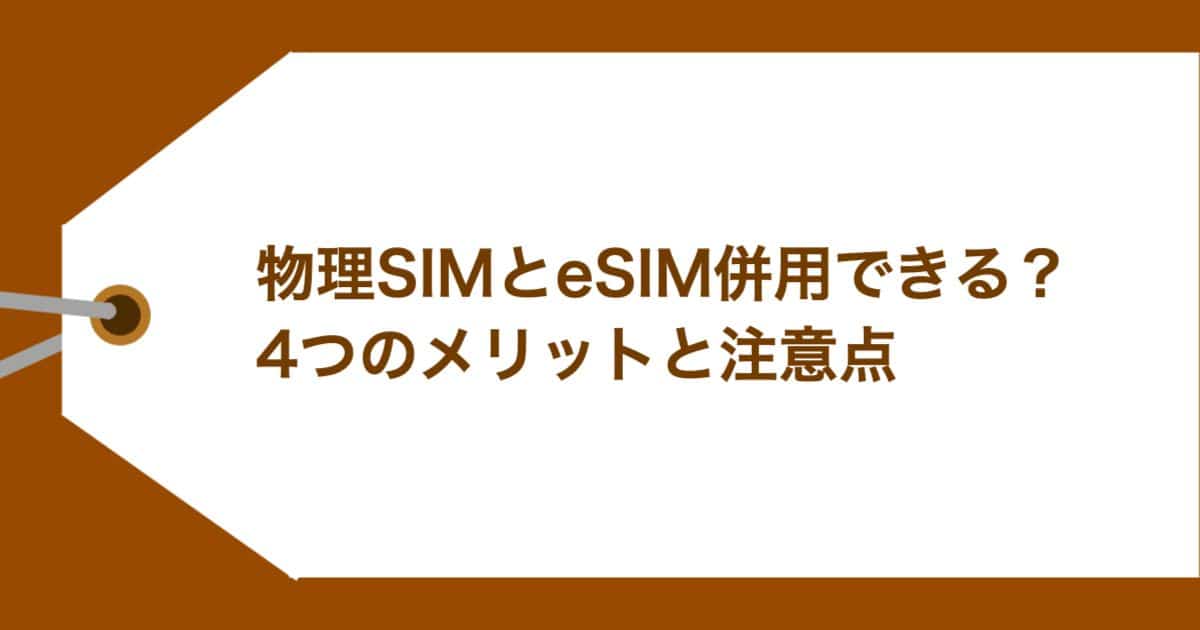
「仕事とプライベートでスマホを使い分けたいけど、2台持ち歩くのは重いし面倒」そんな悩みを抱えていませんか?
この記事で解説する『物理SIMとeSIM併用の方法』を実践すれば、1台のスマホで2つの電話番号を使い分けられるようになります。
実際に筆者は10台以上のスマートフォンで物理SIMとeSIM併用を活用し、通信費の削減や海外での高額ローミング回避を実現しています。
今回は併用のメリットや注意点、対応機種、具体的な設定手順まで詳しく解説します。
物理SIMとeSIMの違いについて
スマートフォンで通信を行うためのSIMには、物理SIMとeSIMの2種類があります。
始めにそれぞれの特徴や仕組みを理解しましょう。
物理SIMはカード型で取り外し可能
物理SIMは、スマートフォンに挿入して使用するプラスチック製のカード型SIMです。
最も一般的なタイプで、ほぼ全てのスマートフォンで利用できます。
カードサイズは標準SIM、microSIM、nanoSIMの3種類があり、現在主流なのはnanoSIMです。
キャリアショップや家電量販店で即日発行してもらえるため、契約当日から使い始められますが、オンライン申し込みだと郵送になるので受け取るまで回線を使う事ができません。
また端末を変更する際は、SIMカードを差し替えるだけで新しい端末でも同じ回線で通信ができます。
例えば万一お使いのスマートフォンが故障した場合でも、SIMカードを抜いて別の端末に挿せばすぐに回線を利用できる利便性があります。
eSIMはスマートフォン内蔵のデジタル型SIM
eSIMは、スマートフォン本体に内蔵されたデジタル型のSIMです。物理的なカードではなく、QRコードを読み取ることで回線情報をダウンロードし、すぐに利用開始できます。
申し込みから開通までオンラインで完結するため、最短即日で使い始められる点が大きな特徴です。APN設定(インターネット接続に必要な設定)も自動で行われるため、初期設定の手間を大幅に省けます。
物理SIMのように紛失や破損のリスクがなく、複数の回線情報を端末内に保存できます。ただし、対応機種が限られているため、事前に自分のスマートフォンがeSIMに対応しているか確認が必要です。
ほとんどのスマートフォンで利用可能ですが、例えばシャオミ X7 Proは物理SIMのみでeSIMが使用できない機種もあるので念のため確認が必要です。
物理SIMとeSIMの併用について
物理SIMとeSIMは、2つのSIMを認識できるデュアルSIM対応のスマートフォンであれば併用できます。
1台のスマートフォンで2つの回線を使い分けられるため、用途に応じた使い方が可能になります。
デュアルSIM機能で2つの回線を同時利用可能
デュアルSIM機能により、1台のスマホで2つの電話番号を管理することが可能です。
両方の回線で同時に着信を受けられるため、どちらかの番号にかかってきた電話を逃す心配がありません。
発信する際は、その都度どちらの番号から発信するかを選択できます。
データ通信については、優先的に使用する回線を設定画面から指定可能です。
音声通話とデータ通信で別々の回線を使うこともできるため、料金プランを最適化できます。
たとえば通話は大手キャリア、データ通信は格安SIMといった使い分けもできます。
1台のスマホで仕事用と私用を使い分けられる
物理SIMとeSIMの併用により、1台のスマホで仕事用とプライベート用の番号を使い分けられます。
スマートフォンを2台持ち歩く必要がなくなるため、荷物を減らせて軽くする事もできます。
使い分けの例として、仕事用には大手キャリアの安定した回線を、プライベート用には料金の安い格安SIMを選ぶことが可能です。
就業時間外はプライベート用の番号だけで着信を受けるといった設定もできます。
連絡先に登録した相手ごとに、発信する番号を指定することも可能です。
取引先には仕事用番号、友人にはプライベート用番号というように、自動的に使い分けられるため操作ミスを防げます。
物理SIMとeSIMを併用するメリット
物理SIMとeSIMを併用することで、料金の最適化やリスク分散など、さまざまなメリットが得られます。
ここでは、併用によって実現できる主な利点を3つ紹介します。
用途に応じて最適なキャリアプランを選べる
物理SIMとeSIMの併用により、データ通信と音声通話で異なるキャリアを使い分けることが可能です。それぞれの用途に最適なプランを組み合わせることで、通信費の削減が期待できます。
たとえば、音声通話は品質の安定した大手キャリアを月額1,000円程度のかけ放題プランで契約し、データ通信は格安SIMの大容量プランを月額2,000円程度で利用するといった使い方ができます。
また、仕事用には通話品質重視のプラン、プライベート用にはデータ容量重視のプランを選ぶことも可能です。
1つのキャリアでは実現できなかった、自分のライフスタイルに合わせた柔軟なプラン設計が実現します。
通信障害時のリスク分散になる
異なるキャリアの物理SIMとeSIMを併用すれば、通信障害が発生した際のリスクを分散できます。
もし万が一、一方の回線が使えなくなっても片方の回線で通信を継続できるため安心です。
最近では2024年に大手キャリアで大規模な通信障害が発生し、数時間にわたって通信できない状況が起きました。
仕事で重要な連絡を待っている場合、仕事ができない状態になりこのような障害は大きな問題になります。
2つの異なるキャリアを契約していれば、片方で障害が起きても別の回線に切り替えて通信を復旧すれば対応可能です。特にテレワークや外出先での業務が多い方にとって、通信手段を複数確保しておくことは業務継続の観点からも重要です。
海外で高額なローミング料金を回避できる
海外渡航時に現地のeSIMを追加することで、高額な国際ローミング料金を避けられます。
日本の物理SIMはそのまま残しておけるため、日本の電話番号での着信も可能です。
国際ローミングとは日本で契約した回線を、海外の現地の通信事業者の回線を使ってそのまま利用できるサービスで、現地に着けばそのまま使えて手間がかかりませんが、国際ローミングを使うとデータ通信だけで1日あたり3,000円前後かかることがあります。
一方、現地のeSIMなら数日間使えるプランが500円程度から購入できるので、大幅なコスト削減が可能です。
渡航前にオンラインで現地のeSIMを購入しておけば、到着後すぐにインターネットが使えます。
日本の物理SIMはデータローミングをオフにしてネット回線を停止し、音声通話のみ有効にしておけば、緊急時の連絡手段として維持できて安心です。
物理SIMとeSIMを併用するデメリット
物理SIMとeSIMの併用にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
併用を検討する際は、以下の注意点を事前に確認しておきましょう。
併用できる対応機種が限られている
物理SIMとeSIMを併用するには、デュアルSIM機能とeSIMの両方に対応したスマートフォンが必要です。
すべての機種で使えるわけではないため、事前の確認が欠かせません。
iPhoneではiPhone XS以降の機種が対応していますが、それ以前の機種では利用できません。
Androidについては、Google PixelシリーズやGalaxyシリーズの一部機種が対応している一方、対応していない機種も多く存在します。
なおeSIMは2021年頃から本格的に普及し始めましたので、目安としてそれより前に発売されたスマートフォンでは使えない可能性があります。
また、eSIM対応機種であっても、購入したキャリアによってはSIMロックがかかっている場合があります。特に購入時期によってSIMロック条件が異なります。
SIMロックを解除しないと他社のeSIMが使えないため、購入時や機種変更時には対応状況をしっかり確認する必要があります。
初期設定に手間と時間がかかる
物理SIMとeSIMの併用には、複数の設定手順を踏む必要があり、初心者には少し難しく感じられることがあります。
物理SIMのように挿すだけで使えるわけではありません。
eSIMを利用するには、QRコードを読み取ってプロファイルをダウンロードし、モバイル通信プランに追加する作業が必要です。
さらに、データ通信と音声通話でどちらの回線を優先するかを設定する必要があります。
これらの設定にはWiFi環境が必要になるため、設定するスマートフォンをWiFi接続する準備が必要です。
また、設定中にエラーが発生した場合、自分で解決するか、契約先のキャリアサポートに問い合わせる必要があるので、接続が完了するまでに時間がかかることもあります。
2つの料金プランを管理する必要がある
物理SIMとeSIMで異なるキャリアを契約すると、2つの料金プランを個別に管理しなければなりません。請求が別々に来るため、支払い管理が煩雑になります。
それぞれのキャリアでデータ使用量を確認し、プランの見直しや変更が必要かを判断する手間もかかります。
契約更新のタイミングも異なるため、いつどちらのプランを更新するか把握しておく必要があります。
また、どちらかのプランを解約する際は、契約期間や解約金の有無を確認しなければなりません。
1つのキャリアだけを使っている場合に比べて、管理すべき項目が増えることに注意しておきましょう。
各キャリアのマイページに契約期間などの情報を確認することもできます。
バッテリー消費が通常より早くなる可能性がある
2つの回線を同時に待ち受け状態にするため、通常よりもバッテリーの消費が若干早くなる可能性があります。
常に2つの回線と接続しているため、端末への負荷が増えるケースもあります。
ただし、バッテリー消費への影響は機種や使用状況によって異なります。
最新のスマートフォンであれば、電力管理機能が優れているため、それほど大きな影響は出ないこともあります。
バッテリーの減りが気になる場合は、使わない回線を一時的にオフにする設定も可能です。
また、モバイルバッテリーを携帯する、省電力モードを活用するといった対策を取ることで、バッテリー消費の問題に対処できます。
物理SIMとeSIM併用できる機種
物理SIMとeSIMを併用するには、デュアルSIM対応の機種が必要です。
ここでは、2023年以降に発売された主要なiPhoneとAndroid機種を紹介します。
iPhone対応機種一覧
以下のiPhoneシリーズは、物理SIMとeSIMの併用に対応しています。
| iPhone 16シリーズ | 2024年発売 | A18チップを搭載し、処理性能とバッテリー持ちが向上しました。 物理SIMスロット1つとeSIMを組み合わせて使用でき、最大2つの電話番号を同時に利用可能です。 カメラ性能も大幅に向上しており、仕事とプライベートで撮影用途を分けたい方にも最適な機種となっています。 |
| iPhone 15シリーズ | 2023年発売 | USB-Cポートを初めて採用したモデルで、充電やデータ転送の利便性が向上しています。 Dynamic Islandを搭載し、通知や進行中の操作を直感的に確認できます。 物理SIMとeSIMの併用はもちろん、eSIMのみでの運用も可能なため、用途に応じた柔軟な使い方ができる機種です。 |
2025年に発売されたiPhone 17シリーズは注意が必要です。
全モデルがeSIMのみ、になり物理SIMを挿入する事はできません。eSIM 2回線でデュアル通信になりますので、SIM契約時に注意が必要です。
Android対応機種一覧
Android端末では、以下の機種が物理SIMとeSIMの併用に対応しています。
| Google Pixel 10シリーズ | 2025年発売 | Googleが開発したTensor G5チップを搭載し、AI機能が大幅に強化されたモデルです。 物理SIMとeSIMの併用設定も分かりやすく、初心者でも簡単に設定できます。 カメラ性能が非常に高く、写真や動画の撮影を頻繁に行う方に適しています。 ソフトウェアアップデートも7年間保証されており、長期間安心して使用可能です。 |
| Samsung Galaxy S24シリーズ | 2024年発売 | 高性能なSnapdragon 8 Gen 3を搭載し、処理速度と省電力性能が優れています。 大画面ディスプレイでビジネス資料の確認がしやすく、仕事用途に最適です。 物理SIMとeSIMの併用時でも、バッテリー持ちが良好で、1日中快適に使用できます。 Sペン対応モデルもあり、手書きメモを頻繁に取る方におすすめです。 |
| Xperia 1 VI | 2024年発売 | ソニーの技術を活かした高品質なディスプレイとオーディオ性能が特徴です。 21:9の縦長ディスプレイにより、2つのアプリを同時に快適に表示できます。 物理SIMとeSIMの併用も動作し、microSDカードスロットも搭載しているため、データ容量を気にせず使えます。 カメラはプロ仕様の設定が可能で、写真撮影にこだわりたい方に最適です。 |
海外で物理SIMとeSIMを併用する方法
前述した通り海外旅行や出張では、日本の物理SIMに現地のeSIMを追加することで、高額なローミング料金を避けられます。
ここでは、海外で併用する際の具体的な手順を解説します。
渡航前に現地のeSIM購入
海外で使用するeSIMは、渡航前にオンラインで購入しておくことをおすすめします。出発前に準備しておけば、現地到着後すぐにインターネットが使える状態になります。
現地の空港やコンビニでも購入可能ですが、到着早々ばたばたしたくない、かつどこで買えるか探す手間もあるので、事前に日本で購入しておくのがオススメです。
また現地のeSIMは、専門サービスのWebサイトやアプリから購入可能です。
主なサービスとして、Airalo、Ubigi、Nomadなどがあり、世界各国のeSIMを取り扱っています。
購入時には渡航先の国、利用期間、必要なデータ容量を選択します。
たとえば5日間で3GBのプランなら500円程度から利用できるため、国際ローミングの1日3,000円と比べて大幅に安くなります。
購入後はQRコードがメールで送られてくるため、渡航前にスマートフォンに保存しておきましょう。
到着後にeSIMを有効化
現地に到着したら、Wi-Fi環境下でeSIMを有効化する手順を進めます。空港の無料Wi-Fiに接続してから作業を始めると、スムーズに設定できます。
iPhoneの場合は、「設定」→「モバイル通信」→「eSIMを追加」からQRコードを読み取ります。Androidでは「設定」→「ネットワークとインターネット」→「SIM」から同様の操作を行います。
プロファイルのダウンロードが完了したら、追加したeSIMをデータ通信の優先回線に設定してください。この設定により、インターネットは現地のeSIMを使用し、電話の着信は日本の物理SIMで受けられる状態になります。
設定後は、ブラウザを開いて実際にインターネットに接続できるか確認しましょう。
日本の物理SIMのデータローミングをオフ
現地のeSIMでデータ通信を行う際は、必ず日本の物理SIMのデータローミングをオフにしてください。
オフにしないと、意図せず物理SIM側でデータ通信が発生し、高額な請求が来る可能性があります。
設定方法は、iPhoneなら「設定」→「モバイル通信」から日本のSIMを選択し、「データローミング」をオフにします。
Androidでは「設定」→「ネットワークとインターネット」→「SIM」から日本のSIMを選び、「ローミング」をオフにしてください。
データローミングをオフにしても、音声通話とSMSは受信可能です。
日本からの緊急連絡も受けられるため安心です。
帰国後は、設定を元に戻すのを忘れないようにしましょう。
ちょっとした一手間で、海外での通信費を大幅に削減できます。
物理SIMとeSIM併用時の注意点
物理SIMとeSIMを併用する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。
事前に把握しておくことで、トラブルを避けてスムーズに利用できます。
機種変更時はeSIMの再発行手続きが必要になる
機種変更を行う際、eSIMは物理SIMのように差し替えるだけでは使えません。
一度認識させたQRコードを再利用できませんので、新しい端末でeSIMを利用するには再発行の手続きが必要です。
物理SIMは新しいスマートフォンに挿し替えるだけで使えますが、eSIMは端末固有の番号に紐づいているため同じ手順では移行できません。
キャリアのWebサイトやアプリから再発行手続きを行い、新しいQRコードを取得する必要があります。
手続きには本人確認が必要な場合もあり、即座に移行できないこともあります。
キャリアによって再発行手数料がかかる場合があります。
年間の再発行回数を超えると有料になるなど、キャリアによってことなります。機種変更の予定がある方は、事前に手続き方法を確認しておきましょう。
なお一部の最新機種では、iPhone同士やAndroid同士でeSIMを直接転送できる機能もあります。キャリアによって転送できる、できないがあるので機種変更前に確認しておくとよいです。
SIMロック解除が必要な場合がある
キャリアで購入したスマートフォンには、SIMロックがかかっている場合があります。SIMロックがかかっていると、購入したキャリア以外のSIMが使えません。
SIMロックとは、特定のキャリアのSIMしか使えないように端末に制限をかける仕組みです。たとえばドコモで購入した端末は、ドコモ以外のSIMが使えない状態になっています。
物理SIMとeSIMを併用する際、異なるキャリアを組み合わせる場合はSIMロック解除が必須です。解除手続きは、各キャリアのWebサイトやショップで行えます。2021年10月以降に発売された端末は原則SIMロックがかかっていませんが、それ以前の機種を使う方は確認が必要です。
両方の回線で同時にデータ通信はできない
デュアルSIM機能では、データ通信を使用できるのは1つの回線のみです。
2つの回線で同時にインターネット接続することはできません。
音声通話は両方の回線で同時に待ち受けできますが、データ通信については優先回線を1つ選択する必要があります。
たとえば仕事用SIMをデータ通信に設定した場合、プライベート用SIMではインターネットが使えません。
データ通信に使う回線は設定画面からいつでも切り替え可能です。
状況に応じて手動で変更すれば、両方の回線のデータ容量を使い分けられます。
ただし、切り替えのたびに設定操作が必要なため、頻繁に変更すると手間がかかることは理解しておきましょう。
通信品質はキャリアとエリアによって異なる
物理SIMとeSIMで異なるキャリアを使用する場合、それぞれの通信品質は利用エリアによって変わります。常に両方が快適に使えるとは限りません。
大手キャリアは全国的にカバー範囲が広い一方、格安SIMは都市部では快適でも地方や建物内で繋がりにくい場合もあります。使う場所や時間帯によっては通信速度が低下する場合もあります。
併用する際は、メインで使う回線は通信品質の安定したキャリアを選び、サブ回線にコストを重視したキャリアを選ぶのがおすすめです。
実際に使用する場所での通信状況を事前に確認しておくと、より快適に利用できます。
物理SIMとeSIM併用に関するよくある質問
物理SIMとeSIMの併用について、よく寄せられる疑問をまとめました。
導入前の不安を解消し、スムーズに利用を始められるよう参考にしてください。
物理SIMとeSIMを併用しても、通信速度が遅くなることはありません。
データ通信に使用するのは1つの回線のみなので、併用が原因で速度への影響は発生しません。
デュアルSIMで2つの回線を待ち受け状態にしていても、実際にインターネット通信を行うのは設定で選択した1つの回線だけです。もう1つの回線は電話やSMSの待ち受けのみを行います。
通信速度は、選択したキャリアの回線品質やエリアによって決まります。たとえば大手キャリアを選べば安定した高速通信が、格安SIMを選べば時間帯によって速度が変動する可能性があります。併用そのものが速度に影響を与えることはないため、安心して利用できます。
もし発生したら別の原因が考えられ、データ通信に設定したキャリアの回線が遅い可能性があります。
もう一方のSIMをデータ回線に切り替えて切り分けなどを行ってください。
着信時には、どちらの番号にかかってきたかが画面上に明確に表示されます。2つの番号を混同する心配はありません。
iPhoneでは着信画面に「主回線」「副回線」といった表示が出るほか、設定で「仕事用」「プライベート用」などの名前を付けることも可能です。Androidでも同様に、SIMごとに名前を設定できます。
電話帳に登録している相手からの着信であれば、相手の名前と合わせてどちらの番号にかかってきたかが表示されます。着信履歴を確認する際も、どちらの番号での着信だったか記録されるため、後から確認することもできます。
1つのeSIMを複数の端末で同時に使用することはできません。eSIMは1台の端末にのみ登録できる仕組みになっています。
物理SIMのように別の端末に挿し替えて使うことができないのがeSIMの特徴です。新しい端末でeSIMを使いたい場合は、キャリアで再発行手続きを行い、新しいQRコードを取得する必要があります。
ただし、端末内には複数のeSIMプロファイルを保存しておくことが可能です。iPhoneなら8つ以上のプロファイルを保存でき、使用する回線を切り替えられます。この機能により、海外旅行時に現地のeSIMを追加して使い分けることができます。
物理SIMを抜いても、eSIMだけで通常どおり通信できます。eSIM単体で音声通話もデータ通信も問題なく利用可能です。
物理SIMスロットは空けたままでも端末の動作に影響はありません。eSIMのみで運用したい場合は、物理SIMを入れずに使い続けることができます。
逆に、後から物理SIMを追加してデュアルSIM環境にすることも可能です。最初はeSIMだけで使い始めて、必要に応じて物理SIMを追加するという使い方もできます。柔軟に運用方法を変更できる点が、eSIMの大きなメリットです。
機種変更時には、物理SIMとeSIMで手続きが異なります。それぞれの移行方法を理解しておくことで、スムーズに新しい端末へ移行できます。
物理SIMの場合
新しい端末のSIMスロットに差し替えるだけで、そのまま使用できます。特別な手続きは不要です。キャリアによってAPNという設定が必要になる場合もありますので、キャリアの開通設定手順を確認しておきましょう。
eSIMの場合
キャリアのWebサイトやアプリから再発行手続きを行い、新しいQRコードを取得します。その後、新しい端末でQRコードを読み取ってプロファイルをダウンロードすれば利用開始できます。
一部の機種では、eSIMを直接転送できる機能もあります。iPhone同士であれば、Bluetooth経由で簡単に転送可能です。事前に手続き方法を確認しておくと安心です。
まとめ
物理SIMとeSIMは、デュアルSIM対応のスマートフォンであれば併用可能です。
1台で仕事用とプライベート用の番号を使い分けられるほか、用途に応じて最適なキャリアプランを選べるため、通信費の削減も期待できます。また異なるキャリアを契約すれば通信障害時のリスク分散になり、海外では現地のeSIMを追加することで高額なローミング料金を回避できます。
ただし対応機種が必要であることや、初期設定に手間がかかる点には注意が必要です。
2つの料金プランを管理する必要もあります。併用を検討する際は、自分の使い方に合ったメリットがあるかを確認し、機種の対応状況や設定方法を事前に把握しておきましょう。
上手に活用すれば、より便利で経済的なモバイルライフが実現します。
物理SIMとeSIM併用で1台のスマホを仕事とプライベートで使い分けられます。通信費削減や通信障害時のリスク分散、海外での高額ローミング回避も可能。対応機種や設定方法、注意点まで詳しく解説します。
